「コストを押さえつつ、効果的に情報を拡散させたい」「SNSで発信しているものの、なかなか話題にならない」といった悩みを抱えている広報PR担当者は少なくありません。また、バイラルマーケティングという手法を知っていても、自然な拡散を生む仕掛けや成功につなげる設計に悩むこともあるでしょう。
本記事では、バイラルマーケティングの種類からメリットや成功のポイント、実際の成功事例までをわかりやすく解説します。
バイラルマーケティングとは
バイラルマーケティングとは、「ウイルス性の」という意味を持つ「Viral」を語源とし、SNSやWeb上の口コミを通じて情報を拡散させるマーケティング手法です。たとえば、共感や驚きを呼ぶキャンペーン動画がSNSでシェアされ、短期間で話題になる現象もその一例です。
ただし、企業が「バズらせよう」と意図的に仕掛けているのが感じられてしまうと、嫌悪感や不信感を招くリスクもあるため、自然に「誰かに伝えたくなる」といった設計をすることが成功のカギとなります。

バイラルマーケティングの種類
バイラルマーケティングには、「企業が発信の起点となる手法=1次的バイラルマーケティング」と、「生活者の自発的な投稿や共感によって広がる手法=2次的バイラルマーケティング」の2種類に分けられますます。どちらの手法においても話題を生み、自然な形で広めてもらう仕組みづくりをすることが成功のヒントに。また実際には、これら2つの手法を組み合わせて拡散を設計をするケースも多く、それぞれの特徴を理解したうえで活用することがポイントとなります。
企業が仕掛ける「1次的バイラルマーケティング」
1次的バイラルマーケティングとは、企業やブランドが発信の起点となり、計画的に話題化を狙う手法です。
企業の公式SNSなどを通じたキャンペーンを展開し、シェアされやすいコンテンツを設計することで、拡散の流れをコントロールしやすいのが特徴です。たとえば、ハッシュタグキャンペーンや企業が制作したユニークな動画をSNSに投稿して話題化を狙う施策などが該当します。
1次的バイラルマーケティングの特徴は、以下の通りです。
- 発信者:企業・ブランドが主体
- 拡散の主導権:企業がコントロールしやすい
- 意図:計画的に拡散を設計
- 拡散の持続性:短期的が多いが、施策の内容によっても異なる
- 成功要因:インパクトのある広告や話題性の高いキャンペーンなど
1次的バイラルマーケティングは、企業の意図や世界観を正確に伝えやすく、再現性も高いことから、ブランド認知の加速が期待できます。ただし、必ずしも話題化するとは限らず、早期に話題が沈静化するケースもあるため、2次的バイラルマーケティングへと発展する設計を併せて検討することが重要です。
ユーザーが拡散を生む「2次的バイラルマーケティング」
2次的バイラルマーケティングは、生活者やメディアによる自然な口コミやUGC(ユーザー生成コンテンツ)を通じて情報が広がる手法です。
企業側が直接的に拡散をコントロールすることは難しいものの、顧客視点でのリアルな声が広がるため、強いエンゲージメントを生みやすく長期間拡散が続く可能性があるのが特徴です。
2次的バイラルマーケティングの特徴は、以下の通りです。
- 発信者:生活者(ユーザー)
- 拡散の主導権:企業がコントロールしにくい
- 拡散の持続性:継続的・長期間(じわじわ広がる場合がある)
- 成功要因:生活者(ユーザー)の共感・話題性・UGCの創出
生活者の投稿をきっかけに話題が広がり、メディア掲載につながるケースもあります。拡散の起点は自然な動機づけを意識した設計にするのが理想です。
バイラルマーケティングと他のマーケティング手法との違い
バイラルマーケティングと似た言葉や施策はいくつかありますが、それぞれの目的やアプローチ方法が異なります。ここでは、特に混同されやすい3つのマーケティングの手法との違いについてを整理しながら、バイラルマーケティングならではの特徴を解説します。
バズマーケティングとの違い
バズマーケティングとバイラルマーケティングは、どちらも「話題化を狙う」という点で共通しています。バズマーケティングは短期間で注目を集めることを目的とするため、一時的な拡散に留まりやすいのが特徴です。一方、バイラルマーケティングは、生活者の共感やUGCを通じて、人から人へ拡散を狙います。
たとえば、企業がインパクト重視のキャンペーンを打ち出すのは、バズマーケティング的な手法といえるでしょう。それに対して、実際に体験したユーザーが「使ってみたらよかった!」とSNSに投稿し始めることで、バイラルマーケティング的な広がりへと発展していくこともあります。
インフルエンサーマーケティングとの違い
インフルエンサーマーケティングは、インフルエンサーを起点に情報を拡散させる手法で、影響力があったり信頼性の高い個人からの情報のため一気に話題になることを期待されます。一方、バイラルマーケティングは特定の個人に依存せず、生活者全体が「自然にシェアしたくなる」仕組みを設計し、人から人への連鎖的な広がりを狙う点が大きな違いといえるでしょう。
それらの性質上、インフルエンサーの投稿は拡散のピークが短期間で収束する傾向がありますが、バイラルマーケティングは共感や実体験が連鎖し、継続的に広がる可能性を秘めています。
たとえばそれぞれの強みを生かすことで、インフルエンサーがコスメを紹介して一気に注目させ、それを見た一般ユーザーが「私も使ってよかった」と投稿。そこから別のユーザーへと拡散していく流れを生むことができるでしょう。
バイラルマーケティングの3つのメリット
バイラルマーケティングは、大きなコストをかけずに自然な形で拡散を狙えるうえ、設計次第では計画的な広がりも生み出せるという強みがあります。ここでは、施策を検討する際に知っておきたい代表的なメリットを具体例とともにご紹介します。
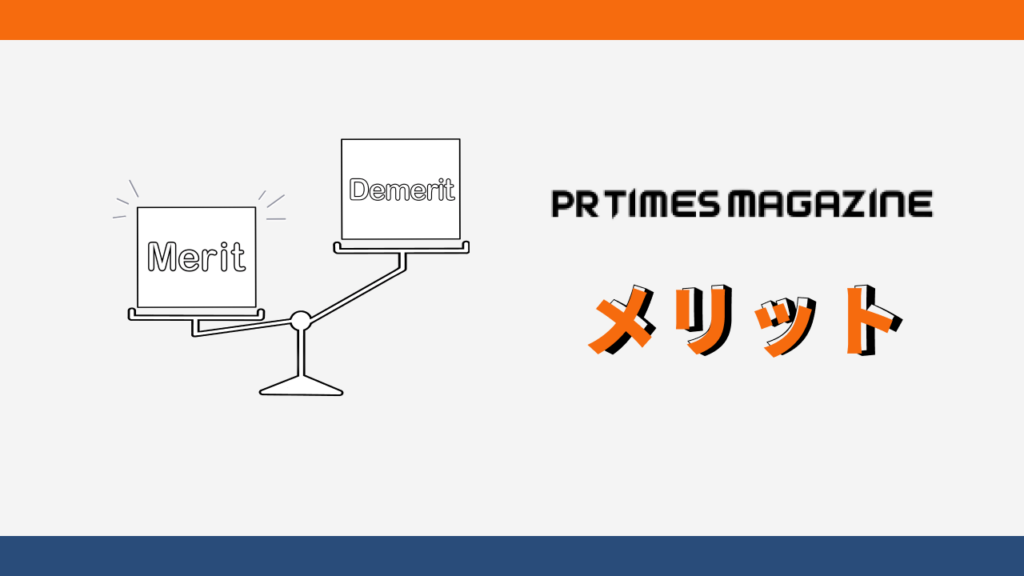
メリット1.費用対効果が高い
バイラルマーケティングは、生活者の自発的なシェアによって情報が広がるため、広告費を抑えつつ大きなリーチが期待できます。
たとえば、企業が制作した動画が話題になれば、制作や投稿以外の追加コストをかけずに拡散される可能性もあるでしょう。さらにUGCや口コミが自然に生まれ、メディアに取り上げられることで、拡散が持続しやすくなる点も魅力です。
1次的バイラルマーケティングで話題の起点を作り、そこから生活者による投稿や口コミへとつながっていけば、結果的に大きなリーチを生み出すことも可能です。
メリット2.計画的に拡散を生み出せる
バイラルマーケティングの強みは、「偶然のバズり」に頼らず、拡散を狙って設計できる点にあります。共感・驚き・感動など、人が「誰かに伝えたくなる」要素をコンテンツに組み込むことで、拡散の確率を高められます。
たとえば、ブランドと親和性の高いインフルエンサーを起点に「〇〇チャレンジ」を企画し、一般ユーザーも参加しやすい仕組みにすれば、自然な拡散の流れをつくることができます。短期的な話題化だけでなく、段階的な拡散導線を設計することで、中長期的な広がりも狙えるでしょう。
メリット3.共感により拡散が加速する
バイラルマーケティングでは、企業の発信だけでなく生活者自身がブランド情報を広めてくれることが特徴です。そのため、広告的な印象が薄く、自然な拡散が期待できます。
たとえば「#私の推し〇〇」など、生活者の体験投稿を促すキャンペーンを実施すればUGCが生まれ、それを見た別のユーザーがさらに発信するという好循環が生まれます。ユーザーの投稿がSNSで注目を集めれば、インフルエンサーやメディアに取り上げられる可能性も高まり、拡散スピードが一気に加速することもあります。
バイラルマーケティングを実施するときの3つの注意点
バイラルマーケティングは高い拡散力を持つ一方で、運用を誤るとブランドにとって逆効果になってしまうリスクもあります。思わぬ炎上や信頼低下を防ぐためには、実施前のリスク管理や発信内容のチェックが欠かせません。ここでは、バイラル施策を進めるうえで特に注意したい3つのポイントを紹介します。
注意点1.ブランドイメージを損なわないようにする
話題性を重視するあまり、ブランドの価値観や世界観から逸脱したメッセージを発信してしまうと、ブランドイメージを損なう恐れがあります。「ブランドとして、どう伝えるのが適切か?」という視点を常に意識することが大切です。
たとえば、ユーモアを狙った投稿が一部の層に不快感を与え、批判が殺到するケースもあります。ブランドのコンセプトやトーン&マナーに沿った一貫性のある内容設計に加え、文化・ジェンダー・社会的背景への配慮も欠かせないポイントです。
注意点2.情報発信の透明性を守る
バイラルマーケティングは自然な拡散が期待できる手法ですが、その分、情報の正確性や透明性の担保が重要です。たとえば、インフルエンサーに商品を紹介してもらう場合、「PR」であることを明記していないと、ステルスマーケティングと誤解されるリスクがあります。
また、実態と異なる投稿や、生活者の声を装った発信はブランドへの信頼を大きく損なう可能性もあるでしょう。口コミやレビューの信頼性を保つためにも、事実に基づいた表現と、自発的な投稿を大切にする姿勢が求められます。
注意点3.リスク管理を徹底する
バイラルマーケティングの大きな魅力である“拡散力”は、裏を返せばリスク拡大のスピードも速いということになります。ネガティブな反応が瞬く間に広がり、ブランドに深刻な影響を与える可能性もあるでしょう。
たとえば、ひとつの言葉や演出が特定の層に不快感を与え、SNS上でネガティブな反応が広がることも考えられます。そのため、施策実施前には表現や内容にリスクがないか丁寧に確認することが大切です。また、万が一炎上などが起きた際でも、すぐに対応できるフローを事前に整えておくと安心でしょう。
バイラルマーケティングを実施する手順
バイラルマーケティングを成功させるには、単に拡散を狙ったコンテンツを作って投稿するだけでは難しいでしょう。重要なのは、「誰に・どのように届け・どのように広めてもらうか」を戦略的に設計することです。ここでは、バイラルマーケティングを実施する際に押さえておきたい基本の手順を解説します。
STEP1.目標と対象者を明確にする
バイラルマーケティングを成功に導くには、「何のために実施するのか」と「誰に届けたいのか」を事前に明確にしておくことが重要です。
「新商品の認知を高めたい」「ブランドの好感度を高めたい」といった成果を明確にしていないと、評価や改善が行えません。対象者層についても、年齢や性別、職業といった属性に加え、どのような価値観や関心を持っているかといった心理的側面にも着目し、具体的に設定することで精度が高まります。
目標設定では、「KGI(最終的に達成したいゴール)」と「KPI(途中経過の指標)」を分けておくことで、施策後の効果測定がしやすくなるでしょう。
具体的な設定例は、以下の通りです。
- KGIの例:関東で就業している20代女性の認知度を20%向上
- KPIの例:1ヵ月以内に3種のSNS投稿のリーチ数を100万回に到達
このように具体的な数字を使って設定することで、チーム内で共通の認識が持ちやすくなります。
以下は、KGIやKPIについて詳しく書かれた記事ですので、併せてチェックしてみてください。
STEP2.配信チャネルと拡散経路の設計
バイラルマーケティングでは、どのチャネルで情報を届けるかによって、拡散のスピードや対象者への到達率などが大きく変わることがあります。
たとえば、10代・20代にリーチしたいならXやTikTok、30代以上が対象であればInstagramやYouTube、Facebookなど、メディアの特性と対象者層に合わせたチャネルを選ぶことが大切です。
また、複数のチャネルを連動させる「クロスチャネル」の活用も効果的です。たとえば、Instagramでビジュアル関連の投稿をします。TikTokでチャレンジ系の動画を投稿し、Xでキャンペーン情報を拡散する、といった導線を作ることで、より幅広い対象者層へのアプローチが可能になるでしょう。さらに、企業公式アカウントだけでなく、インフルエンサーや既存のファン、社員などが起点となれる設計も検討できるとよいでしょう。
「誰から広がるか」が受け手の反応を左右するため、信頼性、親近感、発信力を兼ね備えた人物を選定し、より自然で強力な拡散を生む可能性があります。
以下の記事では、クロスチャネルマーケティングを紹介しています。
STEP3.共感・動機づけの仕掛け設計
「なぜシェアしたくなるのか?」という生活者の視点から、拡散のきっかけを設計することがカギです。
共感・驚き・意外性・お役立ち・社会性など、シェアの動機になりやすい要素を洗い出し、それらをコンテンツに組み込むことがポイントです。
たとえば、「#私の〇〇体験」を公式SNSなどで募集してUGCを促したり、話題性のあるインフルエンサーを起点に拡散の流れを作ったりするのも有効でしょう。他者に話したくなるネタ(シェア価値)を仕掛け、生活者の自発的な拡散につなげる仕組みを整えることが大切です。
STEP4.拡散設計に基づいたコンテンツの企画・制作
STEP3を踏まえ、実際に拡散設計したコンテンツを企画・制作していきます。拡散されやすいフレーズや思わず反応したくなるビジュアル、ストーリーの工夫が求められます。
たとえば、ハッシュタグは拡散を生むかどうか重要な要素ですが、「#わたしの〇〇ルール」や「#〇〇したくなる理由」など誰もが共感しやすいこと、参加の余地を残すことが大切。また、使用する画像は第一印象で伝わるようにインパクトを重視し、動画は数秒で意図が伝わる構成にすることが必要です。企画・制作の際には、投稿のハードルを下げ、拡散を後押しするポイントを意識して生活者の自然な拡散を生み出しましょう。
STEP5.モニタリングと改善
コンテンツの公開後は、拡散状況やユーザーの反応をリアルタイムでモニタリングし、必要に応じて迅速に対応、改善を行います。SNSのエンゲージメント指標(いいね数、シェア数、コメント数)や拡散経路、言及されているキーワードなどを分析し、「どこで、誰に、どう響いたのか」を把握することが重要。
反応が良い投稿があれば強調して再発信し、逆に伸び悩んでいる場合は投稿時間や文言を変えて再挑戦するなど、運用型の調整を加えることも有効です。公開をゴールにせず、思わぬ反響や炎上が起こった場合の対応については事前に決めておくなど、運用体制を整えておくことでより戦略的にバイラルを育てていくことが可能になります。
バイラルマーケティングで口コミを生み出す3つのポイント
バイラルマーケティングで継続的な拡散を生み出すためには、「口コミを生み出すきっかけ」を意識的に設計することが重要です。単にコンテンツを用意するだけではなく、生活者が自発的に発信したくなる仕掛けや導線を整えることで、自然な広がりにつながるでしょう。ここでは、そのための具体的なポイントを紹介します。

ポイント1.共感や驚きを生む体験を用意する
人は、自分が体験したことを「誰かに話したい」「共有したい」と感じる傾向があります。企業からの一方的な情報提供よりも、実際に使った生活者のリアルな声のほうが信頼されやすく、口コミにもつながりやすくなります。
たとえば、新しい化粧品の無料サンプルを配布し、「#使ってみた感想」などの投稿を促す際、想像を上回る体験を提供できると自然な声がSNS上で広がりやすくなるでしょう。また、利用者の体験談を企業側で紹介することも有効です。
このような仕組みづくりにより、まだサービスや製品を利用したことのない生活者にとって「私も試してみたい」というきっかけになるでしょう。
ポイント2.UGCを生むきっかけをつくる
UGCとは、生活者が自ら投稿する写真・動画・レビューなどを指します。企業が直接投稿を依頼しなくとも、自然に投稿したくなる仕掛けを用意すれば、より自然に口コミが広がっていくでしょう。
さらに、ユーザーの投稿を公式アカウントでもシェアすることで、「取り上げられた」という嬉しさが次の投稿を後押しし、さらにその投稿を見た他のユーザーの信頼にもつながります。
また、シェアでポイントがもらえる、投稿でプレゼントが当たるなど、インセンティブを起点にするのも効果的です。生活者が「主役になれる場」を提供することで、拡散のきっかけを増やすことができます。
ポイント3.話題の初速をつくるプレスリリースを配信
口コミを生むためには、まず話題の種を蒔く情報発信が必要です。プレスリリースの配信は、バイラルマーケティングにおける口コミのきっかけとしても有効な手段となります。
新商品の話題性やユニークなキャンペーンがメディアに掲載されることで、生活者への信頼感ある情報提供につながったり、生活者に直接情報が届きSNSでのシェアが増えたりするなど、UGCの拡大にも期待が持てます。
たとえば、「参加型の◯◯チャレンジを開始!」といった企画をプレスリリースで配信し、Webメディアに取り上げられた後にSNSで拡散されるといった流れは、理想的なバイラルマーケティングの展開といえるでしょう。
バイラルマーケティングの成功事例
バイラルマーケティングを成功させるには、「共感を生む仕掛け」と「自然な拡散を促す設計」が重要です。ここでは、企業が実際に展開した施策の中から話題を広げた注目の成功事例を紹介します。
事例1.オリオンビール株式会社
オリオンビール株式会社は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuberグループ「にじさんじ」とのコラボレーションを通じて、SNSキャンペーンやライブ配信、グッズ販売を連動させたクロスチャネルを活用した戦略を展開しました。
事前に「#オリオンビール見つけた」という参加型キャンペーンを実施し、ユーザーのUGCを促進。さらに、ライブ配信当日にグッズ販売を開始することで、話題と購買を同時に加速させる仕掛けを設計しています。複数のチャネルを横断的に活用し、ユーザーの共感と参加を引き出したことで、自然な拡散が生まれた好事例です。
参考:オリオンビール×にじさんじ、初のコラボが実現!花畑チャイカ・ミラン・ケストレル・社築とのコラボグッズを3月30日より発売!
事例2.株式会社Rainmakers
「muice(ミュアイス)」は、株式会社Rainmakersが展開するコスメブランドで、美容系動画クリエイター・かわにしみき氏がプロデュースを手がけています。
muiceの「ちゅるリップランパー」総選挙では、POPUPイベントと連動してユーザー参加型の人気投票を実施。定番化・復刻カラーの決定に生活者の声を反映することで、商品への共感と愛着を高めました。
さらに、再販売決定の発表がSNSでのシェアを促し、自然な拡散へとつながった点もポイントです。ユーザーの「選んだ実感」を活かした設計により、話題性と購買意欲の双方を高めた事例といえます。
参考:美容系動画クリエイター・かわにしみきプロデュース muice(ミュアイス)「ちゅるリップランパー」総選挙で全18色の中から選ばれた人気カラー8色が定番化&限定再販!
事例3.株式会社ABABA
リクルーティングサービスを展開する株式会社ABABAは、人気漫画『トリリオンゲーム』とのコラボレーションで「#トリリオンゲーム最終面接会場」をSHIBUYA109に設置しました。
来場者が撮影・投稿したくなるフォトスポットと、ハッシュタグ投稿によるプレゼント企画を組み合わせ、自然なUGCを促進しています。
さらに、オンライン投稿キャンペーンも連動させることで、オフラインとオンライン両方から拡散の流れを設計。話題性と参加型体験を掛け合わせた事例です。
参考:「#トリリオンゲーム最終面接会場」が渋谷のど真ん中に登場!ダイレクトリクルーティングサービスABABAと漫画『トリリオンゲーム』のコラボキャンペーン!
バイラルマーケティングを成功させる3つのコツ
バイラルマーケティングを成功させるためには、「偶然のバズり」に頼るのではなく、拡散の仕組みを戦略的に設計することが重要です。単に話題性のあるコンテンツを用意するだけではなく、対象者の行動心理や拡散の流れまで見据えた施策設計が求められます。ここでは、実践時に押さえておきたい3つのコツをご紹介します。
コツ1.生活者がシェアしたくなる要素を組み込む
これまで解説したように、バイラルマーケティングでは「誰かに伝えたくなる」要素を盛り込むことが成功させるためのポイントのひとつです。共感や驚き、感動といった感情を動かす仕掛けに加え、社会性や話題性も組み合わせると、より効果的です。
たとえば「#私の推し文房具エピソード」のようなハッシュタグ企画で、生活者自身のストーリーを語ってもらえば、自然な拡散が期待できるでしょう。ほかにも、「〇〇人気投票」や「みんなで決める〇〇」など、参加型の企画は話題になりやすく、拡散も広がりやすくなります。実体験に基づく投稿や参加企画などは共感を呼びやすく、拡散されやすいコンテンツとして有効です。
コツ2.ネガティブな拡散に対するリスク管理
バイラルマーケティングは拡散力が高いため、思わぬ批判や誤解が広がるリスクもあります。たとえば、何気なく使用した表現が特定の層に不快感を与え、SNSなどで批判が拡散する可能性もあります。そのため、発信前の表現チェックをはじめ、万が一のときのための対応フローを準備することは必須といえるでしょう。
また前述した通り、投稿が「ステルスマーケティングでは?」と疑念を持たれないよう、「PR」「提供」などの明記は欠かせません。実体験に基づいた自然な表現を活用し、生活者に対して誠実な姿勢を示すことが、ブランドへの信頼維持にもつながります。
コツ3.拡散を促進する戦略的な設計をする
バイラルマーケティングでは、偶然の拡散に期待するのではなく、「どのように拡散していくか」を事前に設計することが重要です。
たとえば、Instagramで共感を誘うビジュアル投稿を行い、YouTubeで商品の使用シーンを丁寧に紹介、その後Xでの感想投稿を促す、といったクロスチャネルを活用した導線設計により、生活者との接点を増やすことにもつながるでしょう。
さらに、投稿者に特典を提供するなど、UGCを促す仕組みを取り入れることで、継続的な拡散につながるコンテンツへと育てることが可能です。
まとめ:拡散の仕組みの戦略的な設計がバイラルマーケティングの効果を高める
バイラルマーケティングはただ話題性を狙うのではなく、生活者の行動心理や拡散の流れを踏まえた戦略的な設計が成功のカギを握ります。
拡散されやすい仕掛けや参加型の要素、複数チャネルの活用などを丁寧に組み込むことで、短期的な話題化だけでなく長期的な認知拡大やファン獲得にもつながります。
自然な拡散を生む「仕組みづくり」こそが、バイラルマーケティングを効果的に活用する最大のポイントといえるでしょう。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする



